(S3−1)
本文の説明は「です、ます調」で行うと解り難くなってしまうので、一般的な理学書の様に「である調」でおこないます
3 電磁波の実体と発生原理を推理する。
電磁波を波長別に分類するとγ線、X線、紫外線、光(可視光線)、赤外線、電波に別けられる。逆の表現をするとγ線、X線、紫外線、光、赤外線、電波とは電磁波の各波長帯に付けられた名称だという事になる。これらは波長と一波長当たりのエネルギーが異なるだけで種類が異なる訳ではないと考えられる 。
光とは何か、電磁波とは何かと云う疑問に付いては現在においても未だ解明されているとは云い難く、物理学の徒を納得させうる説明に到っていないと考えられる。そこで私はこの疑問に耐え得る答えを推理してみたのでそれを紹介したい。
3−1.今までの理論の検証。
光の波動説と粒子説
光学の分野では光の正体に付いて波動説も有れば粒子説もある訳である。同じものの説明に全く異なる二つの説明が有る訳であるが、なぜ二つの性質が有るかという納得できる説明を未だ誰も為し得ず、未だ説明を一本化出来ていないのである。
マックスウェルの電磁方程式
電磁気学の分野では電磁波の発生原理と伝播原理はマックスウェルの電磁方程式から導かれると云う考えでまとまっており、どの物理学の教科書にもその考えに沿って書かれている。しかし私はこの理論に賛成する事は出来ない。
電磁波伝播に関連するマックスウェルの電磁方程式には、アンペールの実験によって明らかになった「電流の周りの磁界誘導」と、ファラデーの実験によって明らかになった「変動磁界の周りの電界誘導」を数式によって表したものがある。
(S3−2)
マックスウェルの電磁方程式はこれらの実験から知り得た以上の事は何も述べていないのであって、これらの誘導が交互に連鎖的に起こるという事まで述べている訳では無いのである。
私にはここから導かれた電磁波の電磁界交互誘導発生理論は理論の飛躍であると考えられる。もし連鎖的に交互誘導が起こるものと考えると、自己矛盾やその他の困難な問題に直面し、説明に無理が生じるのである。
更にこの理論による電磁波は波としての形を全く有しておらず、又粒子としての性質に付いて何も説明する事が出来ないのであり、物理の理論としては失格と考えられる。その上ここで発生する全ての磁界と二回目以降に発生する電界は結果と原因の二役を交互に継続的に果たす事になり不合理に感じられるのである。
アインシュタインの光量子仮説
アインシュタインは、光は波の様なものではなくて、エネルギーのかたまりが粒子の様になって空間を飛んでいくと云うものであると考え、この仮想粒子に光量子と名付けた。彼がここで述べているエネルギーのかたまりと云う言葉の意味は古典物理学な意味ではなく量子論的な意味である。しかしこのエネルギーのかたまりとは何であるかと云う疑問には何も答えていないのである。
我々は通常エネルギーのかたまりと云う言葉を聞き慣れていてつい何の抵抗もなく受け入れてしまうかも知れない。しかしエネルギーそのものは塊には成り得ないのである。通常使われているエネルギーの塊の意味は大量の石炭や石油等の燃料であったり、元気一杯の人であったりして正確にはエネルギーそのものではない。
(S3−3)
そこで量子論的な意味をはっきりさせる為に、もしエネルギーの意味に古典物理学的な意味が含まれていたらどういう話になるかも付け加えておきたい。古典物理学的なエネルギーの種類には運動エネルギーに属するもの(熱エネルギーも運動エネルギーの一種)と、結合エネルギー(化学的、原子核と電子間、原子核内、素粒子内等など)に属するもの、そして潜在的エネルギーの位置エネルギーがある。
もしエネルギーの意味を運動エネルギーの事であるとすると、運動する物質のかたまりの運動エネルギーを粒子とみなしたという事であり、何か分けの解らない話になってしまう事になる。
もしエネルギーとは結合エネルギーの事であるとすると、光とは物質の結合エネルギーのかたまりが空間を飛んでいきこれを粒子とみなすと云う事であり、これもおかしな説明となる。
位置エネルギーに付いても同様の事が云える。当然の事として、アインシュタインの光量子説には古典物理学的な意味は全く含まれていないと考えられる。
量子論的な光量子の意味
実際的に量子論的な意味は次の様になっている。黒体空洞放射のスペクトル調査実験によると、観測されるスペクトルは温度だけで定まってしまい、空洞を形成する物質や形や大きさによらない。 又、様々な一定温度で実験すると温度毎に僅かずつ異なる山型のスペクトル強度分布が観測される。
ここでスペクトルが強いと云う事はエネルギーが強いと解釈される。そこでこのスペクトルの濃い所にはエネルギーのかたまりが有るとみなして光量子と云う概念が生まれたのであるが、エネルギーの実体に付いては何も解らず、言葉の物理的意味は曖昧なままなのである。
従って、ここでそのエネルギーとは何かがはっきりしなければそのかたまりと云う考えも光量子説も実体不明の仮説になってしまう訳で有る。
(S3−4)
恐らくこの事を深く追求していくと、物質とは何か?エネルギーとは何か?どうしてそれらはこの宇宙に誕生したのかと云う疑問に発展してしまい、未だ我々人類の知り得ない領域の話となるだろう。今の段階では我々は我々の知り得た事実全てに辻褄の合う方法で推理する事が最も健全な方法であると考えられる。
電磁波の電磁気学的な今までの説明
電磁気学の分野に関してはもう少し説明を追加しておいた方が良いかもしれない。
マックス・ボルンは彼の著書「アインシュタインの相対性理論」の中で電磁力が有限の速度で伝わると云う結論がマックスウェルの方程式から導かれると述べている。提唱者はマックスウェル自身であろうか?その所は不明であった。話は真空すなわちエーテル中に限るとなっている。ここでは伝導率σ=0、真電荷ρ=0、誘電率ε=1、透磁率μ=1である。 真空中であるという事はε、μ共に1だと云う事であり、真空には電導性が無いから伝導率σも0だと云う事であると説明されている。真電荷とは分極電荷では無い電荷と解釈した。
ここでのマックスウェルの方程式は
(S3−5)
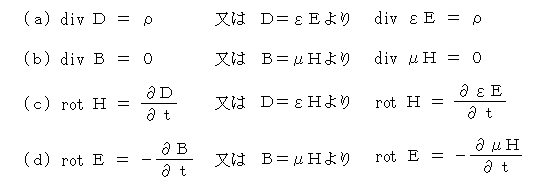
これらは全てベクトル表示であり、div DはベクトルDの発散 rot HはベクトルHの回転の意味である。 (c)に付いては電磁波発生に伝導電流は関与しないと考えたのか変位電流の項のみ書かれている。
これらの式の意味は次の通りである。
(a)真電荷ρから電気変位D=εEが発散している。
電界に関するガウスの定理を表している
(b)任意の閉曲線面を通って中に入ったのと同じだけの磁気変位B=μHが外に出る。入ったものは全て出てしまうので0と云う意味か? 適切な表現法には見えないと思うが。
磁界に関するガウスの定理を表している。
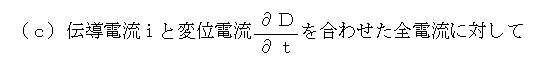
アンペールの法則が成り立つ。この全電流には自らを取り囲む様な磁場Hを誘導するという法則性がある事を表している。ただしこの式には右ネジの方向性と云う意味は含まれない。
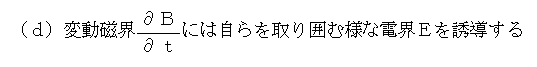
という法則性がある事を表している。
ファラデーの電磁誘導の法則を表す。
(S3−6)
さて私はたったこれだけの意味しか持たないこれらの式をもって電磁波伝播のメカニズムを理論的に明確に解明しようと云うのはそもそも無理な話であろうと考える。 実際これから述べる彼らの電磁波伝播のメカニズムモデルはごく簡単なモデルに留まる。又ここで使用されるのは(c)式と(d)式のみであり、(a)式と(b)式は全く関与していない。
私は真空も静止エーテルの存在も否定しており、電磁波は波であるのだから媒質が必要であって,本当に何も無い所など伝わらないと考えた方が合理的と考えているのであるが、しばらくこの事を不問にしたまま説明を続けたい。さて、前記のごとくに変形されたマックスウェルの電磁方程式を基に電磁波の伝播の模様が以下のごとくに説明されている。
空間のある領域に電場Eが有りそれが微少時間dtの間にdEだけ変化したとするとその変化の速さは
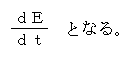
すると次にこのE1の変化により直ちに磁場H1がE1を中心として環状に生じる。 Hの発生は微少時間の間に起こりその変化の速さは
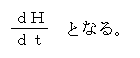
この磁場は再び環状の電場を生み出す。こうして鎖状の現象は有限の速さで続いていく。
図1 モデル1
(S3−7)
|
|
|
但しこの描写は非常に大まかな書き方であって、実際には伝播は全ての方向に連続的に行われるとの断りが有る。 このモデルでは鎖状の輪がだんだん外側へ拡がっていき内側の輪は順次消えていくものと受け取れる。 より詳しい図は図3の様に成ると説明されている。
この様な波が存在する為には 電流によって作られる磁界は 電流の変化と同時には変化せず僅かの遅れが有ると考えなければならない。
この遅れは力学的な弾性波の慣性による遅れに似ている。もしこの遅れが無ければ距離に関係なくあらゆる地点に最初のdt時間で到着しなければならなくなるが実際にはそうではないからである。
だが残念ながらこのモデル1はビオ・サヴァールの法則とは融和しないのである。 ビオ・サヴァールの法則とは1820年にフランスのビオ (J.B.Biot)とサヴァール(F.Savart)によって明らかにされた法則であり、その内容は次の通りである。
電流Iの流れている導線の微小部分dsによって点Pに生じる磁界の方向(正しくは向き)はアンペールの右ネジ法則によって決まりその強さdHは
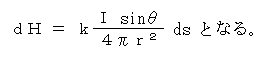
ただしkは比例定数、rは導体素片からP点までの距離、θは導体素片の方向とrの方向とのなす角である。次図参照。
(S3−8)
図2
|
|
|
ここで云う電流とは定常電流の事であるが、スパーク電流も同じに考える事が出来る。 融和しない理由はビオ・サヴァールの法則では最初の中心電流によって生じる磁界は距離の二乗に反比例し,距離に制限は無く広がっているのに対し、ボルンの説明する電磁波モデルでは一つ一つの広がりはすぐに終わっている。 その為磁界の方向に付いて見た場合ビオ・サヴァールの法則では中心から見て右ネジ方向だけなのに対し、電磁波モデルでは鎖状の為交互に反対向きになっている。
一つの電流部分から相反する二つの電磁現象が同時に生じる事は無いと考えた方が合理的なのでどちらかは正しくないと考えられる。私はこの電磁波モデルの方に難点が有ると考える。
モデル1のより詳しい図とは次の様な図である。
図3 モデル2
|
|
|
図の説明
二つの金属球の間にスパーク電流が流れると アンペールの右ネジの法則に従う様な磁界が電流の周りに生じる。 図には二次元のものだけしか書かれていないが、より詳しくは球状の立体的な拡がりになっている。
(S3−9)
次にこの磁界の変化により電磁誘導が起こり磁界の周りに電界が生じる。この電界は玉ねぎの皮の様な半球状となるがここで再び難点が生じる。電磁波がどんどん拡がっていき巨大な距離になった時この玉ねぎの皮状の半球も巨大なものにならなくてはならない事になる。
例えば100億光年の距離からの光は半径100億光年の極めて薄い玉ねぎの皮状になってしまうのである。皮状の表裏を一周すると628億光年の距離になる。もし可視光線であればその薄さは1万分の数ミリ・メートルしかないし、γ線に到っては1000億分の数ミリ・メートルの薄さしかない事になるのである。しかしその様な玉ねぎの皮が発生するとはとても考え難い。
モデル1とモデル2には違いが有る。モデル1の磁界の中心は無数に出来る様になっているが、モデル2の磁界の中心はただ一つである。つまり別物なのである。
多分モデル1をより詳しく書くつもりが間違えてしまったので有ろうか? モデル1は鎖状になって連続しているがモデル2は鎖状にはなっておらず連続していない。 モデル2では相互誘導の連鎖現象が起きる様にはなっていないのである。 正しく書くと次の様になる。
図4 モデル3
(S3−10)
|
|
|
しかしこの様に正確に書くとアンペールの右ネジの法則やビオ・サヴァールの法則と融和しない事が一層明瞭になる。
これらのモデルには未熟な点が有ると考えられ、更にもう一つの欠点が有る。 磁界を誘導する電流の中心は磁界の輪の中心を通らなくてはならないし、電気力線を誘導する磁力線の中心は電気力線の輪の中心を通らなくてはならない。
輪の端の方を通る様な事は有り得ないだろうと考えられるのである。だがモデル1では端の方を通る様に書いてある。
もしモデル1を修正して中心を通る様に書いたとすると中心には互いに逆向きの二つの流れが通る事になり弱い方は完全に打ち消されてしまう事になる。 従ってモデル1の様な鎖状の相互作用は起こりにくいものと考えられる。
それともうまい具合に時間的なずれが有って片方づつしか発生しないとでも受け取らなければ成らないのだろうか?
これらのモデルによる電磁波はそもそも波としての形に欠けているのである。縦波でもないし、さりとて横波でもない。その様な波が現実に存在すると考えられるであろうか? 又更に粒子としての特徴も持っていない様に見える。
(S3−11)
これでは物理学の理論として通用するとはとても云い難い。一口に電磁波は電流の作る磁界とその後の電磁相互誘導とによって生じると考えられているとは云っても、良く調べてみるとその考えは決して一つにまとまっている訳では無くその解釈に多少異なった考えに別れている。
その中の一つは次の様になっている。高校物理の有力参考書に書かれていたものである。
これは電界の様子を書いたものである。
図5 モデル4
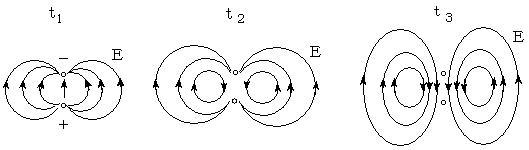
t3 の火花間隔には自己誘導でしばらく電流が流れ続け+−が逆になる。このモデルでは中央で半サイクルの電流しか流れない場合でも電気波は1サイクルになりやや引っ掛かりを感じる。
このモデルでは電気力線の輪と磁気力線の輪がワンペアでだんだん外側へ広がっていく様になっており、鎖状に繋がっているわけではない。従って電界と磁界はお互いに一方が他方を生ずる様に発生していると云う説明に反しそうではない事が分る。
(S3−12)
3−2.私の推理した電磁波の発生理論
私は電磁波発生のメカニズムを次の様に推理する。
電磁波のメカニズムは、スタート時における単振動発生のメカニズムと、その単振動が次々と隣へ伝わっていき元の単振動は順次消滅していく事により波が形成されると云う二つのメカニズムにより成り立っていると私は考えるが、初めに何故単振動が発生するかに付いてそのメカニズムを推理する事から始める。
図6 ファラデーの電気力線。
|
|
|
図7
|
|
(S3−13)
図8
|
|
|
図9 波が隣へ伝わる様子。
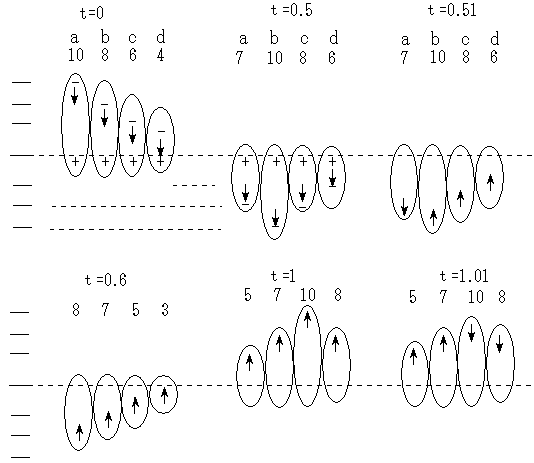
僅かに離した二つの金属球を高電圧の異種電荷で充電し火花放電させ電磁波を発生させたとする。火花放電前の周囲電界の様子は図6の様になっており、ファラデーの電気力線に沿って周りの気体分子や原子は分極し図7の様になっている。
(S3−14)
次に火花放電が起こると同時に金属球の異種電荷は消滅しその為周りの分極は元に戻ろうとする事になり、戻り変位電流が生じる事になる。この戻り変位電流によってアンペールの右ネジの法則に従う様な磁界が発生する事になる。図8参照。
これが次々と外側へ広がっていく事が電磁波発生の本当のメカニズムではないかと私は推理する。
しかしこの波の振動は摩擦等の抵抗により減衰しない限り同じ場所でいつまでも続く事にもなってしまうのである。
そこでなぜ波動がほとんど同じ強さで次々と隣へ伝わっていき、元の波は次々と消滅していき、後は何事も無かったかの様に静まり返るかと云う説明が必要となるが(これは波の共通性質の問題)、それは次の様に考えられる。
基本的な考え方として、分極の戻りは全ての距離で同時に起こる訳では無く、中心部から端の方へ少しずつ時間的に遅れて起きていく。
その為中心部の分極の戻りは進行方向にある隣の分極分子あるいは分極原子や分極原子核等より早く起こり、その為進行方向隣に力を及ぼし運動エネルギーを伝え、自らの振動運動はその分減少して次第に消滅する、これが次々と隣へ伝播していくのが波であり、遠くへ伝播していく事の出来る理由であると考えれば合理的に説明出来る。この考えを基に推理を進める。
同じ種類の電荷同士は斥力を及ぼし合うと云う性質が有る為、各々の分極原子の外側電子は、隣り合う原子の外側電子とお互いに斥力を及ぼし合う、つまり圧力を及ぼし合う事になる。
(S3−15)
火花放電の周りの分極度は火花放電地点から離れるに従い距離に反比例し少しずつ弱くなっている。
逆に云うと火花放電地点に近いほど分極度は強い事になる。
従って火花放電直後に周りの分子の分極度がゼロに戻ろうとする際、火花放電側に有る分極分子の電子は外側の分極分子の電子より少しずつ斜め上に有る為、斜め上から圧力を及ぼしながら減速する事になり、つまり自らにブレーキ掛けながら減速する事になり、その結果1サイクルの周期タイムも伸びる事になる。
外側の電子は斜め上からの圧力により加速されエネルギーは増加し、1サイクルの周期タイムは反対に短くなる事になる。
説明を簡単にする為分極原子のみを取り上げて考察してみよう。なお分極原子の振動は中心部に有る質量数の大きな原子核の振動とその周りに有る質量数の小さな電子の振動によって成り立っている。振動の中心はお互いの共通重心となる。
図9は火花放電直後のゼロサイクルから1.01サイクル(1サイクルよりほんの僅か後と云う意味に受け取って頂きたい)までの分極原子の分極度合いを大まかに表している。火花放電装置はaの左側に有るとする。t=0 ではa−b−c−dの順に分極の度合いは低くなっているし、同じ順番に分極は解除されていく。
その際aの分極電子はbの分極電子に後ろ斜め上から斥力で圧力を及ぼす。その為bの電子は加速され運動エネルギーをもらいt=0 からt=0.5へ変わった時分極度の大きさは8から10へと増大しているとする(これらは仮の値)。その時aの電子の分極度は逆に10から8未満へ減少している。
そしてaの周期タイムは長くなっている為 t=0.5より僅かに遅れてaの分極度は最高値の0.8になるが、その時にはbの分極度は0.8より少なくなっており、例えばt=0.6の図の様になっていてaは再びbの後ろになりbを後ろから押し自らのエネルギーを消滅させていく。
(S3−16)
こう云うメカニズムにより波動は次々と伝播していく。
この伝播の仕方は水面上を伝わる波と同じである。水面波の力の源は主として重力によるが、極めて小さい波の場合には表面張力も影響すると考えられる。
この二つの推理による私の電磁波説は電磁波が横波であると云う説とも辻褄が合うし、光の粒子としての性質も、自然光の偏光現象も難無く説明出来る。横波に波としての性質と粒子としての性質が有るのは当然の事であり、電磁波の場合も水面の波の場合も共に同じ性質を有す。
水面の波はゆっくりしているので分かり難いが、もし周期が光の様に短くなれば水面すれすれの物体は波に弾き飛ばされる。つまり粒子がぶつかって弾き飛ばされたのと同じ現象が生じる。
電磁波の発生は何も火花放電に限らないので、その他のケースの推理も行っておかなければならない。全ての物質は温度毎に異なる波長の光を放出していると考えられている。
自然の法則は単純で電磁波発生のメカニズムは一つしかないと推理すると、全ての電磁波発生のメカニズムは分極の変動(つまりは電気振動)と、分子や原子や原子核の振動に基づくと考えられ、分極の変動時に発生する変位電流と誘導磁界、そしてそれと一体となる分子や原子や原子核の振動が電磁波の実態と考えられる。
高温となった物質は光を放出するが、その理由に付いても推理してみる。高温物質の分子は激しく分子振動をしている。もし物質の周りに透明気体が充満していたとすると物質の分子振動は周りの接触する気体分子を振動させ、自らの振動エネルギーを周りへ伝える事によって自らの振動エネルギーは減少していく。
電気的には振動や衝突による歪で分極が生ずると推測される。
気体中へ伝えられた分子振動はそこに留まる訳ではなく波として遠くへ伝播していくと推理すればうまく事実を説明出来ると考えられる。
又、物質が振動エネルギーを放出し続ければ当然物質の温度も徐々に冷えていく事になる。この考えは高温物質からエネルギーが光子と云う粒子の形で飛び出て冷えていくと云う考えとは全く異なる。
偏光現象の分析
偏光現象とは次の様なものである。自然光は光線に垂直な面内では方向性が無いが電気石を通ると偏った方向性を持つ様になる事が知られている。次図参照。
図10。
|
|
|
電気石を通る前の光は完全な光であって電気石を通って偏光した光は不完全な光なのだろうかという疑問を持つ人はいないだろうか? もしそう考えると何か不自然であるように考えられる。
私はこの事に付いて次の様に考える。
単色光はそれ以上の振動数に分ける事の出来ない ただ一つの単純な光のように考えられているが、実はそうではなく、同じ振動数を持った複数の波の集まりであると。そしてその個々の波はまちまちの方向で振動しているし、波の山や節等も揃ってはいないのではなかろうかと。
(S3−18)
私が考えた電磁波の原理に基づいて考えれば光には方向性が有る事になる。一つの光波には一つの方向しか無いのであるが、光源からは多くの光波が次々とランダムに発生しておりそれらの振動方向は360度それぞれまちまちなのでは無かろうかと考えるのである。
光の粒子性に付いても、電磁波が分子分極や原子分極や原子核分極の急速変動であり、これは電子や原子核の振動がその実体で有ると考えればこれもうまく説明出来る。
又、長波長でサイクルが長い場合は分極の変化はゆるやかでありエネルギーは少なく、短波長でサイクルが短い場合は早くなりエネルギーは多くなる。
戻り変位電流は全ての区域で同時に流れるわけでは無く中心部から遠ざかるほど時間的な遅れがでる。
物理の理論は関連する全ての事実に完全に辻褄が合わなければならないので、電波の場合はどうなっているかも推理する。
電波の様に波長の長い電磁波の場合はアンテナの様に大きなサイズの電波発信機が必要となり、この場合アンテナ内では変位電流ではなく伝導電流による電気振動となる。
火花放電の場合も発信時点では絶縁破壊による伝導電流である。しかし電磁波として伝播していく段階では分極振動による変位電流しかない。短波長電磁波の場合は小グループ単位の分極振動で、長波長電磁波の場合は大グループ単位の分極振動になると考えられる。
例としてヘルツの発信機を取り上げてみよう。ここでコンデンサーの片方から片方へ電流が流れるのが半サイクルなのであるから、コンデンサー極板が長ければ半サイクルの時間は長くかかり長波長となり 極板が短ければ短波長となる。アンテナに付いても全く同様であると考えられる。
もう一つ付け加えると電磁波の伝播は原理的には絶縁体内でのみ発生する。光の場合に付いて考えると透明気体や透明液体や透明固体等がそうである。伝導性不純物の混じった液体は伝導性を示すがそれでも絶縁物質が連続して存在していれば電磁波はそこを伝播していくと考えられる。電磁波のシールドは金属等の伝導性物質でのみ成し得る事が出来る。
私の理論から導かれるもう一つの重要な内容は電磁波の伝播には媒質が必要で、何も無い真の真空を伝わる事は無いと云う事である。
アインシュタインの考えは、電磁波は波ではなく粒子であり何も無い空間を飛んでいくと考えたものであった。私の考えが正しければ相対性理論は物理学的に見て根本的に間違っていると云う事になり崩壊せざるをえない事になる。
(S3−19)
力学や光学や電磁気学の基礎的な面に関しては現在も一世紀前も余り変わっていないのであるが、この様な情況の中で約一世紀前相対性理論は誕生したものであると私は考える。
相対性理論に対する反論は別途まとめた420ページ程のものを近い内に書籍として発表する予定。ヘルツの発信機等その他の詳しい内容に付いてはその中で述べたい。
3−3. 近い将来発行されるかもしれない私の反論書は次の様な方達にお薦めします。
1・整理されていて解り易い相対性理論の解説書をお探しの方。
2・相対性理論が良く解らない方。
3・相対性理論は絶対に正しいと考えている方。
4・相対性理論の賛成者達が馬鹿な事を云っているくせに賢者ぶっているのが癪に障るので彼らをへこましてやりたいと考えている方。
5・相対性理論は時代遅れで非科学的なので、そんな事よりもっと役に立つ物理学の問題に付いて聞きたいと考えている方。
6・物理学や科学の世界には数百年間未だ誰も解いた事の無い問題が数多く有りますが、そういう問題を解くのに興味のある方。例えばこのホームページで取り上げた電磁波の原理の様に。私はその他にもコマの原理、天体力学の問題等面白い色々な問題を易しく明快に解いていきます。
7・推理小説が三度の飯より好きな方。(物理学の本質は合理的な推理ですので。)
8・文部省のお役人の方。
9・天文学や宇宙論の好きな方。
10・その他理由は問いません。
以上 2004年11月5日 著者 T・Kinoshita 東京にて。